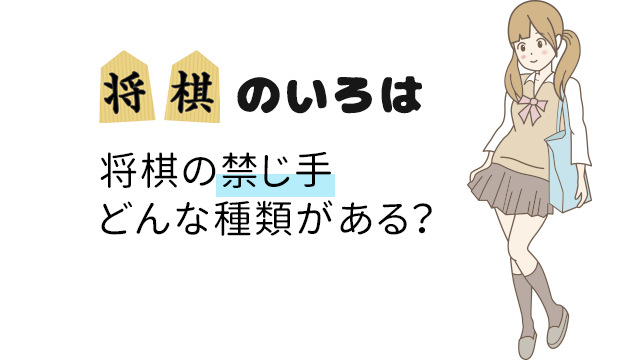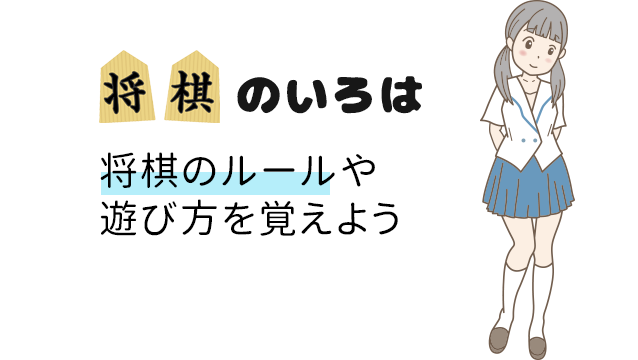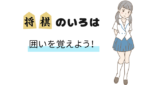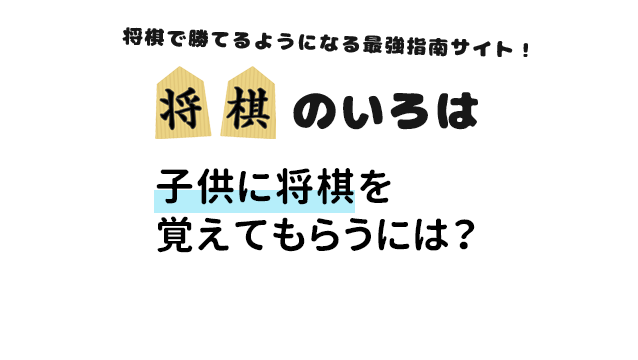今回は、将棋における序盤の指し方と狙いについてご紹介していきます。
飛車の位置、玉の囲い方をこれまでご紹介してきました。
囲い方は定石と呼ばれるような、駒の動きがある程度決まっているので、覚えてしまえば簡単に作ることが出来ます。
いずれ、それぞれの囲い方の定石なんかもご紹介していきたいと思います。
将棋初心者が最初にひっかかる最大のポイントとも言われる序盤。
初心者でもできる、序盤~中盤の駒の動かし方についてご紹介します。
このサイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。
囲った後にどの駒を動かしていけば良いのかわからない
飛車を動かしたり、玉をしっかりと囲いはしたものの、どの駒から進めていけば良いのかわからない人って多いと思います。
意外と本では説明されていませんし、定石や本を読んでも初心者のうちは、相手が定石と全然違うところに指してきて、何をすれば良いのかわからなくなることもあります。
それは、対応だけ書いて、最終的な目的を書いていない本が悪いと思いますけどね。
まず、序盤の考え方を目的をはっきりとさせましょう。
先手番と後手番で目的が若干異なる
先手番、後手番というのは将棋の先行/後攻をあらわす言葉です。
どちらも変わらないように思う人もいらっしゃるでしょうが、持つべき序盤の目標は異なるのがポイントです。
先手番は攻め込むことを目標
先手番を持ったら、目標にして欲しいことがあります。
それは攻め込むことです。
何故なら、玉を詰まないと将棋というゲームでは勝てないのですから。
しかし、ここでの攻め込みというのは、玉を狙うための攻め込みではありません。
序盤から玉を狙っていっても、固い守り遮られ駒損になる可能性も高いです。
ですから、どうやって玉を詰むのかということを逆から考えていくと、序盤の目的が分かりやすくなります。
最終目標は玉の詰みです。しかし、玉は囲われていて、ただ無闇に突っ込んでは返り討ちに合います。
玉の親衛隊となる金や銀が守っているので、これらの駒を崩していく必要があります。
金や銀は万能な駒で、常に駒ごとが連携を取っています。
連携を断ち切るには、好きな場所に打てる持ち駒が必要です。
さらに、金銀の周辺には、攻めの強力な飛車や角がいるので、いつでもカバーにやってきます。
となれば、飛車や角が直ぐに駆け付けられないように、距離を離してあげないといけません。
狙うは飛車や角です。※取るのが目的ではなく、飛車や角の利きをなくせるだけでも効果十分。戦場に引っ張りだすか、使えないようにしてしまう。
しかし、飛車や角の前には、歩による壁があります。とにもかくにも、この壁を突破しないと、お互いに攻め込むことが出来ない。
あなたがやらないといけないことは、玉を詰むこと。
しかし、玉を詰むために歩の壁を突破するのではないことに注意してください。
玉の詰みを狙いながら、仲間探しが最初の目標です。
序盤の攻め込む目標がなんとなくわかってきましたか?
あとは、先手番であることを活かして、相手の薄い筋を狙っていきます。
後手番は隙のない守りでチャンスをうかがう
将棋の後手番は先手番より一手送れることになります。
そのため、先手番と同じように序盤の目標を攻め込みと思って駒組を進めると、無理攻めになりやすいです。
後手番は序盤から攻めるよりは、相手に合わせて隙を伺うようなスキルを求められます。
先手番が急戦を仕掛けてきたら、そちらに付き合わないといけませんが、相手が持久戦をしようとしてきたら、後手番に攻めるチャンスがやってきます。
もちろん先手番に付き合って、守りを固めるというのも一つの手になりますね。
浮き駒を作らないように動かしていく
ここからは、攻め込んでいくための準備について解説していきまs。
攻め込むために、歩の壁に穴をあけることが必要です。
しかし、歩だけをつかって攻めていっても、返り討ちに合うだけです。
将棋のセオリーとして、浮き駒を作らないという考え方があります。
浮き駒というのは、自分の駒が取られた後に、相手の駒を取り返せない状態です。つまり、無防備な状態の駒のことを浮き駒と言います。
基本的に駒が一人で進むことはありません。
お互いをカバーし合えるような相方も一緒になって動きます。
典型的な戦法が棒銀と呼ばれる戦法で、銀と歩の連携を使って攻めていき、銀に繋がっている飛車で一気に叩き込むという手段です。
棒銀には初心者が覚える基礎がつまっていると言われるのはこのためで、取られても取り返して、攻めを継続できるように動かしていくのが序盤のポイントです。
すると、相手も自分の駒を取られても取り返せるようにするため、駒同士を連携させようとします。
相手も浮き駒を作らないように動かす訳ですね。
これが、将棋の基本的な動き方です。
駒というのは単体では弱く、狙われてしまうので、必ずカバーできるような駒を添えます。
ここに、序盤のねらい目をつけるポイントがあります。
駒のカバーに入るということは、必ずどこかの駒が動くということなんです。
狙いを変えていく
浮き駒を作らないように、相手はカバーできるように守りに入りますよね?
そんな時は、狙いの筋を見直してみましょう。
カバーに入ったことで、他の筋が手薄になることもあります。
もちろん、そのまま狙った筋に攻撃を仕掛けるのも良いでしょう。
その時は、攻め側と守り側の駒の数を確認します。
将棋というのは、1手1駒しか動かせないので、基本的には1つしか相手の駒を取ることが出来ません。
つまり、駒ごとに価値は違うとは言え、駒の攻撃力は「1」しかないんです。※王手と駒取りを狙った、1石二鳥のような状態になると、攻撃力は「2」として見れるかも知れません。
攻撃力が1しかないのですから、数が多い方が自然とその場での攻め合いには勝ちまs。
そのため、数で勝っていない場所での攻めは避けた方が良いです。
じゃあ、どうするのかというと、別のところを攻めだすんです。
もちろん、相手は新しく攻め立てられようとしている場所を守ります。
そうしたら、別の場所を攻めます。
駒の数には限りがあります。ですから、攻めを続けていけばカバーが間に合わない場所が出来るんです。
そこが狙いどころで、そういったカバーが間に合わない場所を攻めこむと、最初にカバーに入っていた駒を見捨てて、戦いが起きている場所に移すのもテクニックの一つです。
そうです。最初に狙っていた場所が手薄になるので、さらに狙っていくという感じです。
自分の駒もこの時点でたくさん動いている訳ですから、自分にも隙ができてしまいます。
となれば、攻めてばかりはいられませんよね。
こうやって、お互いに駒の取り合いが開始するのが中盤という訳です。
序盤の駒の動かし方が分からないという方は、目標となる攻めのポイントを一つに絞り過ぎていませんか?
こっちがダメなら、こっちからも攻める。そういった風に小さな戦火を広げていくことが大切です。
中盤で強くなるには、手筋を身につける
序盤の手筋や定石もあるのですが、あくまでも将棋初心者と考えるのであれば、浮き駒を作らないという動かし方で良いはずです。
時間がかかったとしても、必ずどこかでかち合います。
初心者において、最も大事なのは中盤です。そして、中盤を楽しめないと、将棋って楽しくないと思います。
では、中盤に大事なのは何かというと・・・・
相手の駒を取るためのパターン。つまり手筋を身につけることです。
将棋というのは、1手1マスが基本です。ただ追いかけていっても捕まらないどころか、返り討ちにあいます。
ですから、駒を取る手段を覚えないと、どう動かしていけば良いのかわからないですし、攻めていっても返り討ちに合ってしまうこともありまs。
詰将棋も大事ですが、どうやれば相手の駒を取れるのかという、次の一手が知識として必要です。
本で学ぶも良いし、実戦で学ぶも良いです。
大切なのは、どうして取れたのか?どうして取られたのかを知ることです。
こればっかりは、駒の動きの相性によって発生することなので、ひたすら覚えていかないといけません。
将棋の手筋は覚えるのが大変という人は浮き駒探しから
手筋って覚えるの大変だと思います。本にのっているような場面になることが少ないので、身につけ辛いんです。
読んで終わりになりやすいのが、将棋の勉強を楽しくさせていない理由だとも思います。
そこで、はじめのうちに手筋を覚えなくても中盤を楽しむコツが、浮き駒探しです。
どこに動かして良いのかわからない場合は、相手の浮き駒を探してみてください。
初心者同士の対局であれば、必ずどこかにお宝(浮き駒)が眠っています。
浮き駒を見つけたら、相手の駒に気を付けながら狙っていきます。
相手に狙いが気づかれて、守りに入られたら別の場所を狙っていきます。(手筋を学んでいれば、カバーに入られても攻め込む手段に気付けたりします。)
浮き駒が一切なければ、浮き駒をつくることを目指してください。
作り方の代表として、持ち駒の「歩」を使うというものがあります。
あえて、相手の駒の目の前に歩を置くなど、歩を捨てるような使い方をすることで、相手の駒に動きが見られるはずです。
そうやって、価値が低いとされる駒を使って浮き駒を作っていきます。
慣れていないうちは、取られても良い歩を使っていきましょうね。
歩はお互いの持ち駒として最も貯まりやすい駒です。最初は歩の手筋から覚えていくのが上達の秘訣なのかなとも思います。
また、歩の手筋は盤面に影響する範囲が狭いので、覚えやすいというのもオススメの理由です。
様々な駒を取れるパターンを覚えて終盤を有利にしよう!
終盤は先に詰んだ方が勝ちなので、中盤に駒を多く取っていても負けることもあります。
中盤が上手くいっても、負ける対局ってあるんです。
でも、中盤に奮闘できた対局って楽しいんです。負けたら悔しいけど、それ以上に、将棋が指せてるっ!って思えて楽しくなるはずです。
初心者の方は、詰み方の仕組みだけ覚えていれば最初は良いと思います。
次回は終盤について軽くお話して、それから先は覚えやすい簡単な手筋から紹介していきたいと思います。
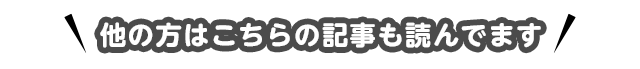
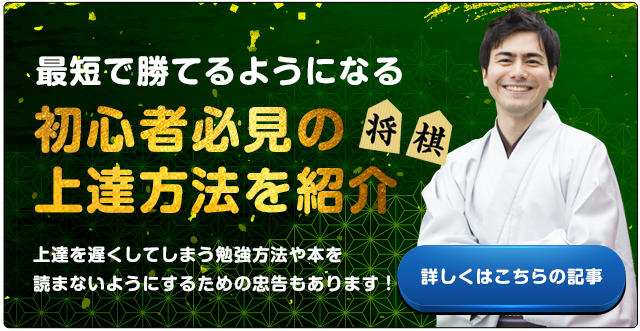 将棋の効率的な勉強方法を解説!初段、二段を目指す人にオススメの将棋学習法
将棋の効率的な勉強方法を解説!初段、二段を目指す人にオススメの将棋学習法

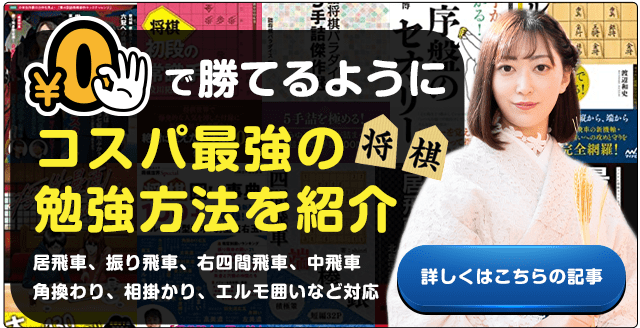 将棋の効率的な勉強方法を解説!初段、二段を目指す人にオススメの将棋学習法
将棋の効率的な勉強方法を解説!初段、二段を目指す人にオススメの将棋学習法