今回は将棋の駒の一つ、香車の動かし方についてご紹介します。
また、香車を使った手筋の解説や、成香の動きも紹介しているので将棋初心者の方から中級者まで参考にしてみて下さい。
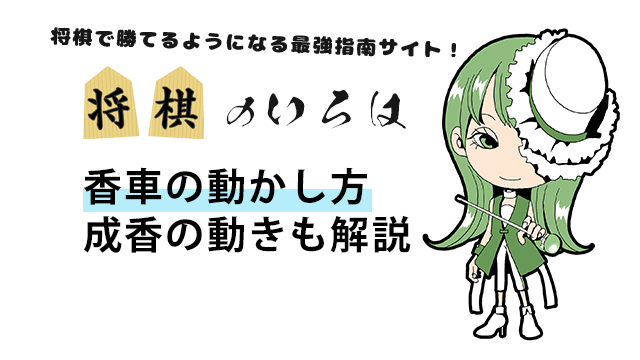
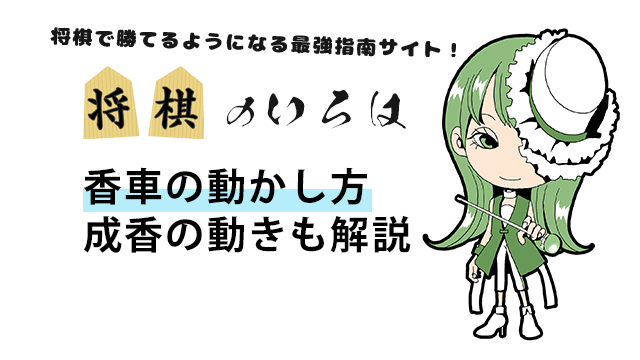
今回は将棋の駒の一つ、香車の動かし方についてご紹介します。
また、香車を使った手筋の解説や、成香の動きも紹介しているので将棋初心者の方から中級者まで参考にしてみて下さい。
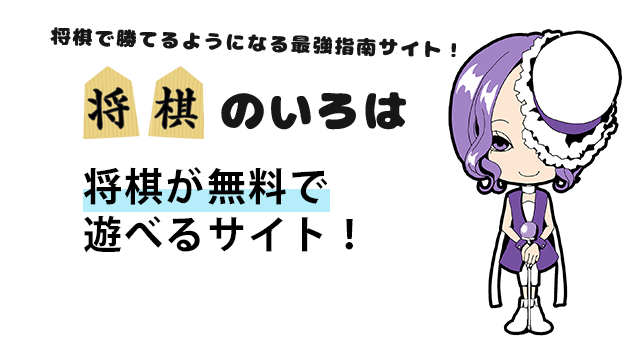
今回は、ブラウザ上で将棋が無料で遊べるサイトをご紹介します。
ふと将棋を指してみたいなと感じた時や、友達と将棋で対戦したいなと思った時に使える無料サイトをご紹介します。
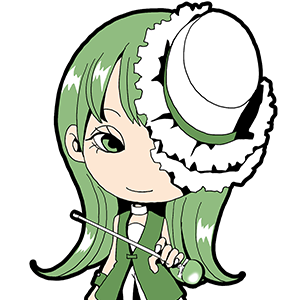
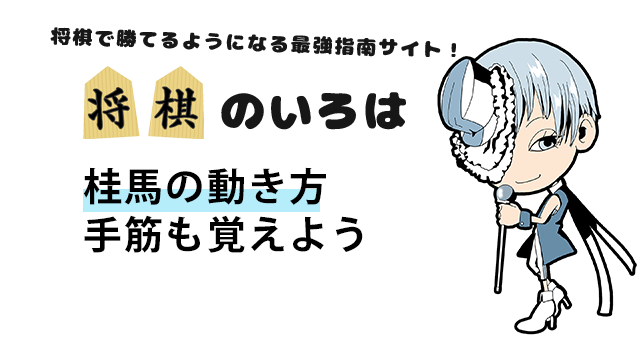
今回は桂馬の動かし方について解説していきます。
将棋の中でも特殊な動きをする桂馬は、進む方向を覚えるのに苦労する駒の一つです。
それでは、桂馬の動き先、そして桂馬を使った手筋も見ていきましょう。
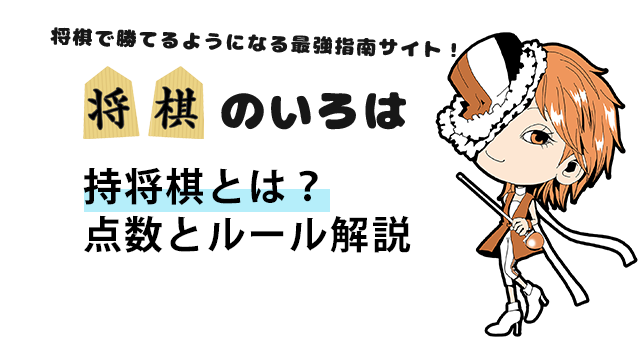
今回は将棋における引き分けルール、持将棋について解説します。
チェスに引き分けがあるように、実は将棋にも引き分けがあります。
それでは、どういった条件で持将棋が起きるのか、過去の対局であった持将棋についてご紹介します。
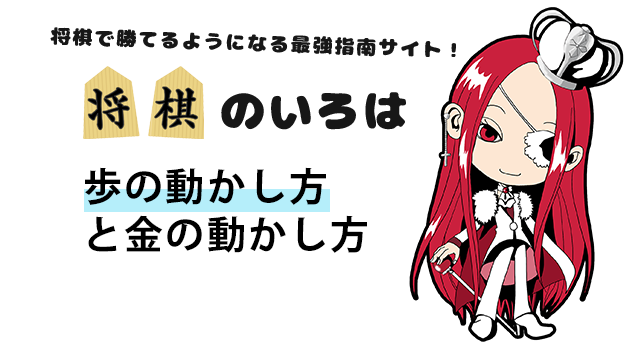
将棋の駒の1つ、歩の動かし方について解説します。
歩は1人9枚持っており盤面を制圧していくためにも使う重要な駒になります。
シンプルながらも大切な歩の使い方を覚えましょう。
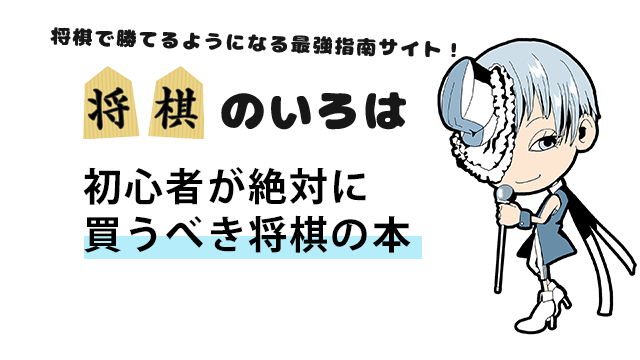
将棋の上達に欠かせない本ですが、販売されている物の中には初心者は読まなくてもいい本だったり、読んでも上達に繋がらないような本も多いです。
今回は、将棋初心者が上達するために欠かせない本のカテゴリとお勧めをご紹介します。
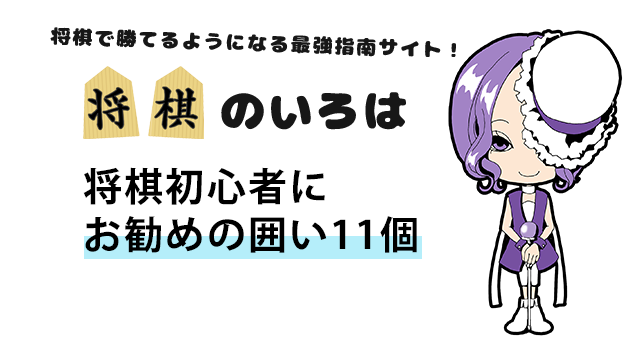
将棋を始めたけど何から勉強すればいいのかわからないという方にオススメしているのが、玉の囲い方を覚えることです。
今回は、将棋の初心者の方にオススメしたい最強の囲いをご紹介します。
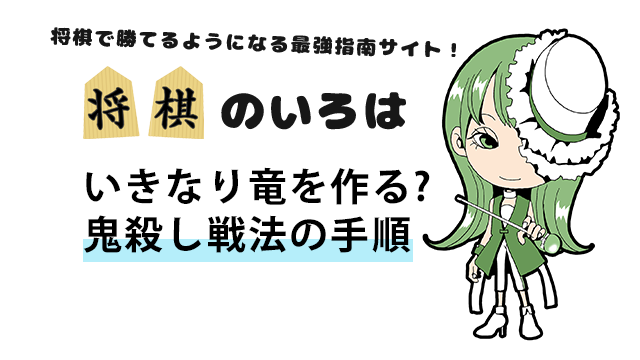
将棋の鬼殺しという戦法をご存知でしょうか?将棋初心者や級クラスの相手を一瞬で倒してしまうハメ手の1つと言えます。
今回は、そんな鬼も倒してしまうという将棋の戦法、鬼殺しの手順と狙いにちて解説します。
鬼殺しを覚えることで得られるメリット
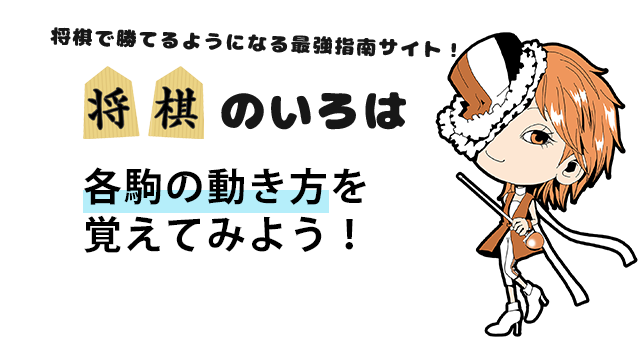
将棋を遊べるようになるためには、各駒の動きを覚える必要があります。
今回は、玉将から歩までの計8種類の駒の動きを丁寧に解説します。
また、将棋の駒の動かし方をまとめたら一覧表もあるので是非参考にしてみてください。
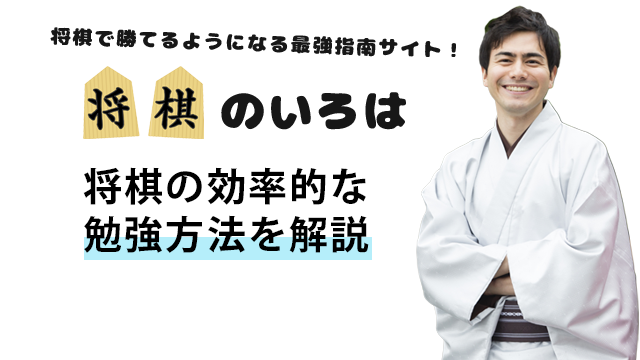
将棋で強くなりたい、対局で勝てるようになりたいと思っている方へ、今回はとっておきの効率的な勉強方法をご紹介します。
将棋において強くなるのに欠かせないのは将棋の本です。
戦法の本、囲いの崩し方の本、詰将棋の本など棋力アップに本は必要不可欠です。
というのも、私が将棋ウォーズで対局ばかりしていた時、1級あたりで躓いたんです。
なかなか初段に上がれず、ただ対局して解析しているだけじゃ上達が遅いなと感じていました。
そこで、本を使って深い戦術を身に付けようと思ったのが今回の方法を利用したきっかけです。
効果は絶大で、1級で躓いていたのに初段、二段と上がることが出来ました。
将棋の本の著者は、ほとんどがプロの棋士です。ですから、真剣師故の戦い方や勘を知識として身に付けることができ大局観が鍛えられたんだと思います。
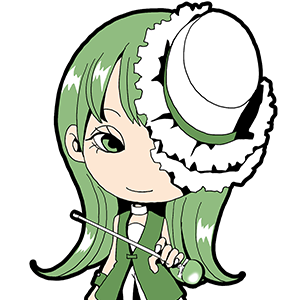
しかし、本を一冊一冊揃えるとなると意外と良い値段になりますよね。
今回は、お墨付きの将棋で強くなるための最強にコスパの良い勉強方法をご紹介します。