今回は将棋ウォーズの棋譜をダウンロードしたり、将棋ソフトに取り込む方法をご紹介します。
棋譜の活用や保存方法がわかるともっと将棋ウォーズが楽しくなるのでしっかりと覚えてみましょう。
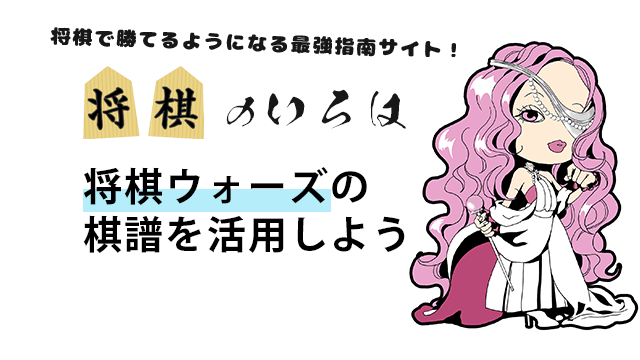
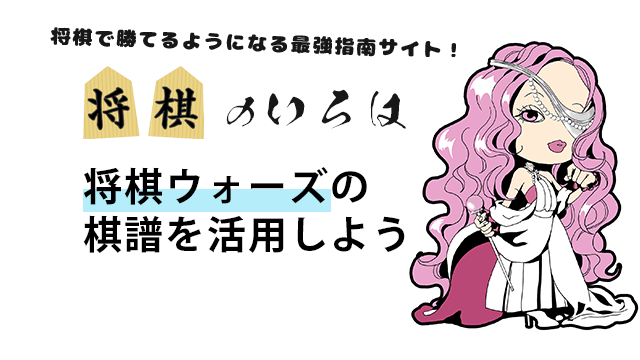
今回は将棋ウォーズの棋譜をダウンロードしたり、将棋ソフトに取り込む方法をご紹介します。
棋譜の活用や保存方法がわかるともっと将棋ウォーズが楽しくなるのでしっかりと覚えてみましょう。
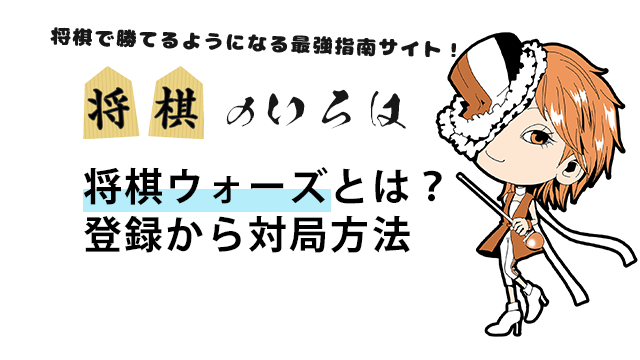
将棋の対局アプリで最もオンライン人口が多いとされている将棋ウォーズ。
様々な機能が搭載されている反面、初心者からすると機能が複雑で何から始めれば良いのか分からないという方もいます。
今回は、将棋ウォーズの特徴から使い方まで詳しく解説していきます。
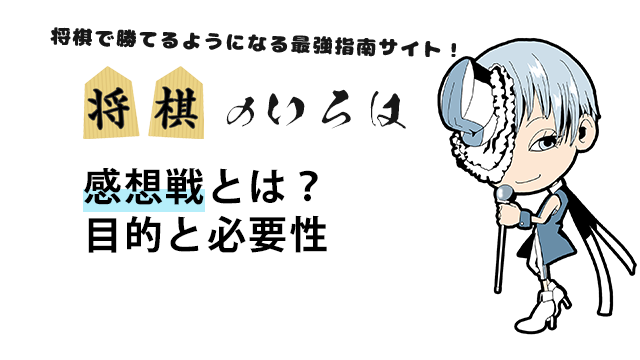
将棋の対局が終わった後に振り返りとして行う感想戦。
今回は、感想戦とは一体なんなのか、そしてなぜ行うのかについて解説していきます。
後半には実際に感想戦のやり方などもまとめているので、将棋上達に活かしてみて下さい。
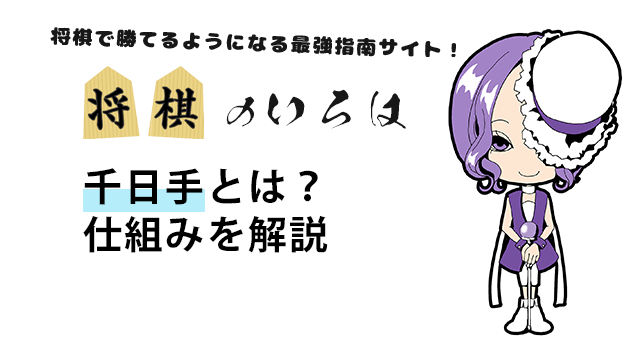
今回は将棋のルールの一つである千日手について解説します。
同じ局面が4回連続訪れると対局が終わってしまう千日手とはどういったルールなのでしょうか?
また、プロ棋士の対局でも千日手はありえるのか解説します。
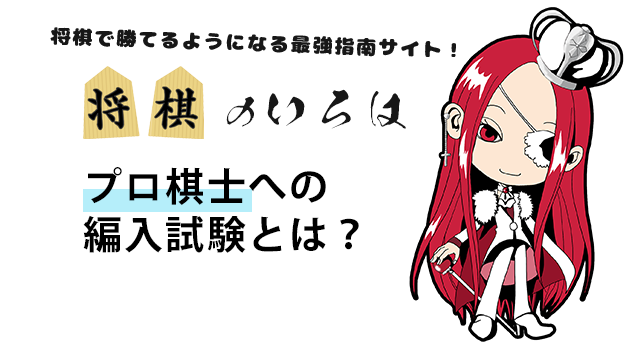
プロ棋士になるためには奨励会に入り、三段リーグで上位2位になることが一般的ですが、その他の手段として棋士編入試験という制度が採用されています。
今回はプロ編入試験改め棋士編入試験制度について詳しく解説していきます。
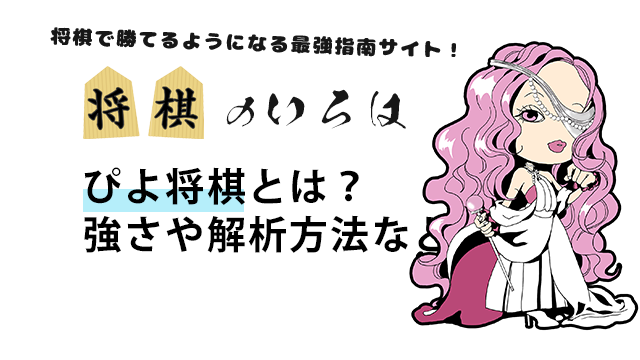
将棋アプリの中でも使い勝手の良さと細かい棋力設定が可能なぴよ将棋。
今回は、ぴよ将棋の機能解説をしながら、将棋で強くなる方法についてもご紹介します。
ぴよ将棋の解析の精度が気になる、初段の強さはどのくらいなのかと疑問を持っている方は参考にしてみてください。
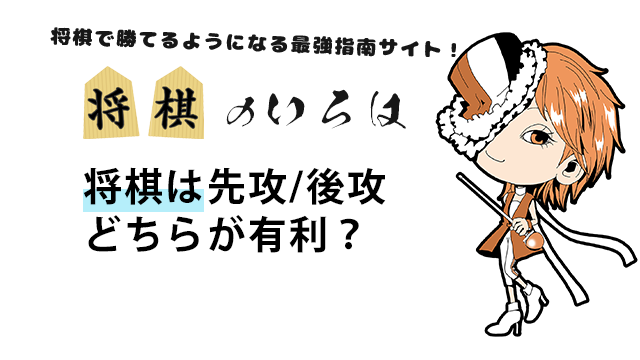
今回は、将棋において先攻と後攻のどちらが有利なのか、そしてプロの世界ではどのようにして有利差をなくしているのかを解説していきます。
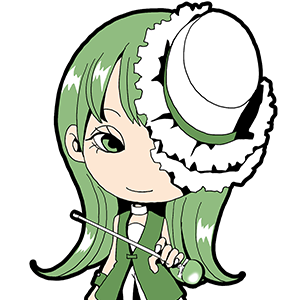
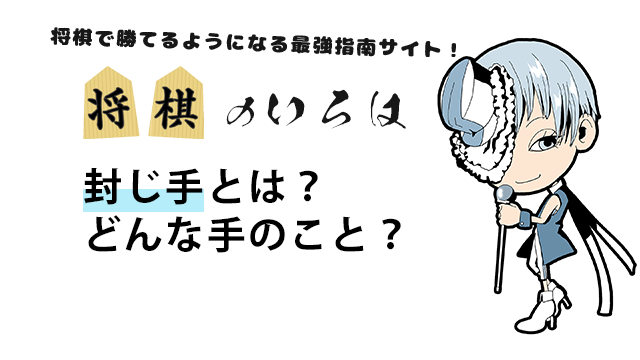
今回は将棋における封じ手のルールについて簡単に説明します。
今回、封じ手についてわかること
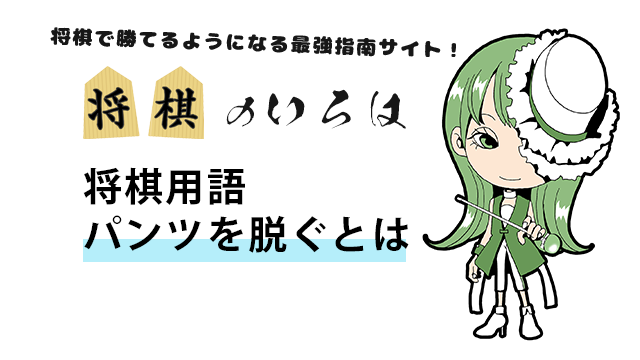
今回は、将棋のパンツを脱ぐという将棋用語について解説していきます。
過去には将棋ウォーズでエフェクトを消されるなんてこともあったパンツを脱ぐの意味を知りましょう。
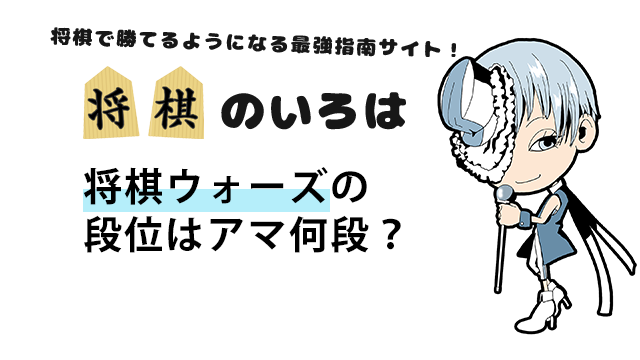
将棋ウォーズに導入されている段級位制のシステムをご存知でしょうか?
将棋ウォーズ内での自分の強さをあらわすのですが、将棋ウォーズの段級位はアマチュアの段級位と同じ強さなのか、もしくは違う強さなのか棋力の目安をご紹介します。